 引越しのタイムスケジュール
引越しのタイムスケジュール
業者選定と下見
家族帯同の場合は、赴任者の荷物の発送と家族の荷物の発送が別になり、たいていの場合、赴任者の出発後、家族が家財の引越手配をしなければならない。赴任が決まった早い段階で、引越作業について家族で話しあっておく必要がある。
引越しの手順はケースバイケースだが、だいたい次のように行われる。
まず、海外引越しの実績がある信頼できる引越業者へ電話をして、引越しの相談・依頼・打ち合わせをする。その後、実際に自宅に来て下見をしてもらい、見積りを出してもらう。その段階で、荷出し(発送)の日も大まかに決めておくが、学校の春休みと夏休みは異動シーズンなので、土曜・日曜・祝祭日など希望の殺到する日は早めに申し込もう。 下見に来てもらう前に大まかに考えておくことがある。船舶貨物(船便)で預けるものは出国の2~4週間前に手元を離れ、現地で受け取るのは赴任して1~2週間後である点が、国内の引越しと大きく異なるからである。約1か月間の「臨時生活」をどうするかについて、計画を立てよう。
船便で送る荷物のほかに、出国の6か月以内に航空便で荷物を送る「航空別送荷物(アナカン)」という方法もある。料金は少し高くなるが、発送から約2週間後に現地で受け取れる。 予定にもとづいて「船便で送るもの」「航空便で送るもの」「手荷物で携行するもの」「国内の倉庫に預けるもの」「国内の親戚などに送るもの」、さらに「廃棄処分するもの」などを決めておく。
引越業者の下見のとき、船便で送りたいものは「この押し入れの上の段」「このタンスと中身全部」「この食器棚の、ここの食器」というふうに説明できないと、引越業者も見積もりに困ってしまうのである。
引越荷物を送る場合、荷物の重さ制限あるいは経費限度額などの規定を設けている企業・団体が多いので、事前に勤務先に確かめておこう。また、もし夫が家族より先に赴任していく場合、夫の使うものから別送航空便で送るようになる。
荷物の仕分けと梱包
荷出しの日から逆算するかたちで準備の予定を立て、荷物の仕分けを始める。赴任して現地に着くまで不要なものから整理していくとよい。
梱包は業者に任せた方が安心。梱包明細書(パッキングリスト)も同時に作成してもらえる。しかし、人に触られたくない物(下着、趣味の道具など)や書類は自分で行う。特に書類関係は、入出国時や在留届の提出時に必要な物を梱包されてしまうと大変なことになるため、十分な注意が必要である。
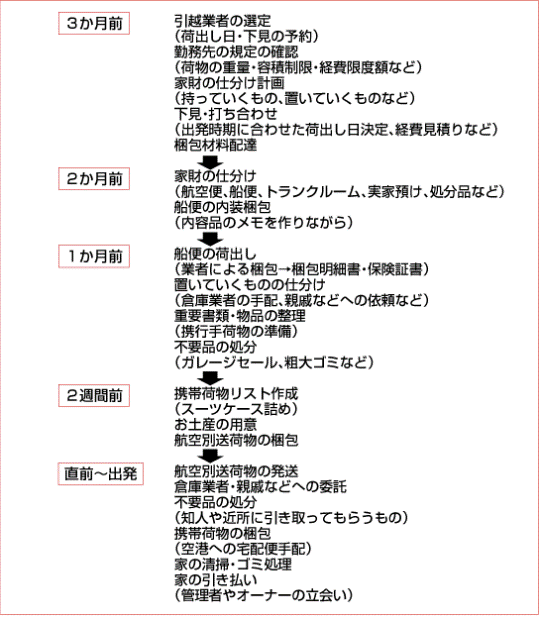
荷出し・通関・輸送
荷物を発送する際には、通関(日本の港・空港と赴任国の港・空港)手続きのためにパスポート・航空券のコピー、梱包明細書(パッキングリスト)などが必要になる。
荷出しの日、引越業者は残りの梱包をすませ、梱包明細書(下書き)と保険申請書類を完成させてくれる。仕向国により、通関用のフォームに署名が必要な場合もある。パスポートの写しなどとともに荷物を預ければ、あとは業者が、日本の通関から現地への輸送までやってくれる。
赴任先に運ばれた荷物は、引越業者または引越業者が提携している地元の運送業者などが通関処理を行い、指定の場所まで配送してくれる。 空港や港での荷降ろし待機、課税対象物品や輸入禁制品のトラブルなども起きやすいが、問題が起きてもきちんと対応してくれる引越業者を、選ぶようにしたい。
残ったものの処置
引越業者に預けなかったものは、さらに「手荷物で携行するもの」「国内の倉庫に預けるもの」「国内の親戚などに送るもの」などに仕分けしていく。出発の日から逆算して予定を立て、国内の倉庫業者への手配や荷造り・発送などを進める。不要なものは知り合いに譲ったり、ガレージセールなどで処分したりする。廃棄処分するものは、市区町村役所に連絡をとって粗大ゴミとして出すか、あるいは専門の業者に引き取ってもらう。
海外赴任生活をサポートしている企業・団体
| 株式会社リロ・エクセル インターナショナル | TEL03-5312-8702 |
|---|












